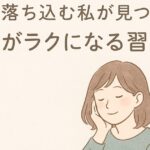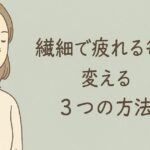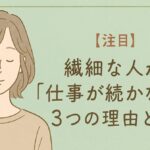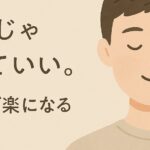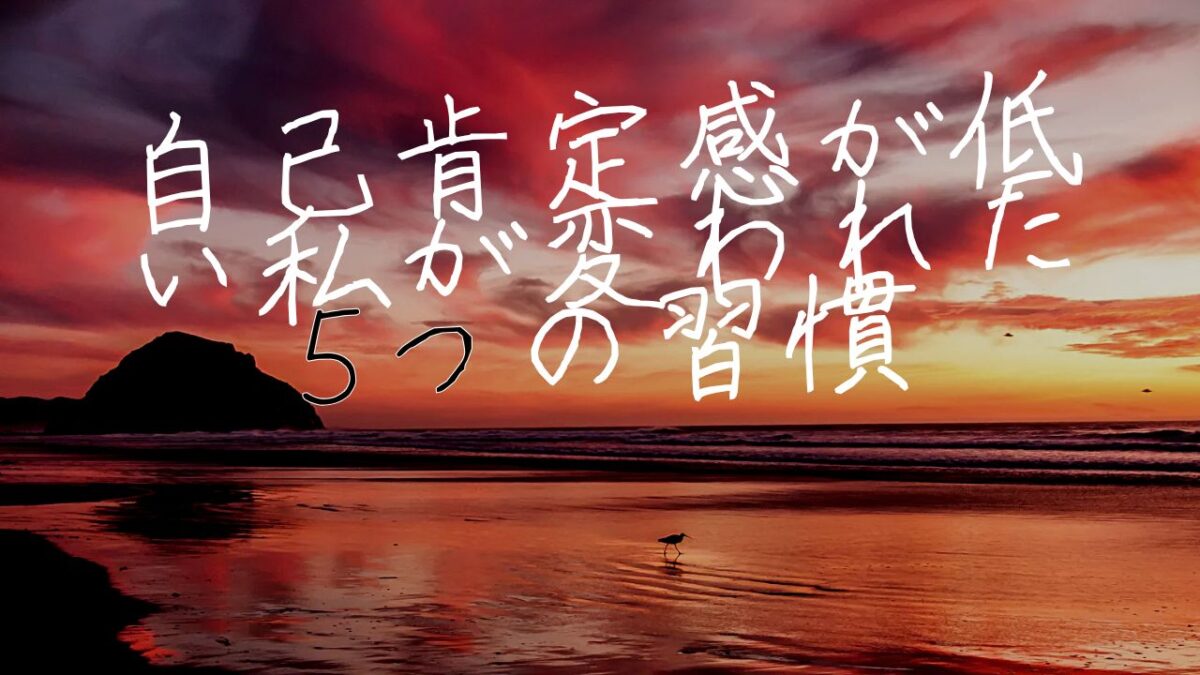
かつて私は毎日自分を責め、他人の顔色ばかり伺っていました。
自己肯定感が低いため、何をしても自信が持てず、いつも不安でした。
しかし、小さな行動を重ねることで、自分を認められるようになり、気づけば前向きな自分に変われていました。
この記事では、そんな私が実際に取り入れて効果を実感した方法を紹介します。
あなたも必ず、自分を好きになれる日が来ます。
自己肯定感が低い原因と特徴

「なぜ自分はこんなにも自信が持てないのだろう?」
自己肯定感が低いと、こうした疑問や苦しさが常につきまといます。ですが、自己肯定感の低さには必ず「原因」と「特徴」があります。
まずは、その仕組みを知ることで、今の自分を受け止めるヒントを見つけましょう。
自己肯定感が低くなる主な原因
自己肯定感が低くなる背景には、さまざまな要因が考えられます。特に次のような経験や環境は、大きく影響を与えます。
- 幼少期の環境
親から十分に認められなかったり、過度に厳しく育てられたりすると、「自分は価値のない存在だ」という思い込みが生まれやすくなります。 - 学校や友人関係での経験
いじめや仲間外れ、成績の不振などの経験が積み重なることで、劣等感が強くなる場合もあります。 - 失敗体験や挫折
大きな失敗をした経験があると、「どうせまた失敗する」という恐れから、新たな挑戦を避けるようになり、自己肯定感が下がってしまいます。 - 完璧主義の傾向
「もっとできるはず」「こうでなければならない」と自分に厳しすぎる考え方も、自分を認めにくくする原因になります。
これらは誰にでも起こり得ることであり、決して珍しいことではありません。大切なのは、「原因があるから今の自分がいる」と理解することです。
自己肯定感が低い人に見られる特徴
自己肯定感が低い人は、日々の言動や考え方に以下のような特徴が表れやすくなります。
- 他人と比較して落ち込みやすい
SNSや周囲の人と自分を比べてしまい、「自分は劣っている」と感じやすくなります。 - 褒められても素直に受け取れない
「たまたまだよ」「私はそんな人間じゃない」と、相手の言葉を否定してしまう傾向があります。 - 失敗を恐れて挑戦を避ける
「またダメだったらどうしよう」という不安から、チャレンジする前に諦めてしまうことが多くなります。 - 承認欲求が強く、人の評価を気にしすぎる
「嫌われたくない」「悪く思われたくない」という気持ちが強くなり、相手の反応ばかりを気にして行動してしまいます。 - 物事をネガティブに考えがち
少しの失敗や指摘も「自分はダメだ」と必要以上に深く受け止めてしまいます。
こうした特徴は、自己肯定感が低いがゆえの「防衛反応」のようなものでもあります。だからこそ、まずは自分の考え方や行動パターンを冷静に見つめ、「そういう傾向があるんだな」と受け止めることが、改善への第一歩になります。
自己肯定感が低いと起きる問題

自己肯定感が低いと、日常のさまざまな場面で「生きづらさ」を感じやすくなります。特に影響が大きいのは、人間関係と仕事(または学校)の2つのシーンです。
ここでは、自己肯定感の低さがどのような問題を引き起こすのか、具体的に解説します。
人間関係で苦労する
自己肯定感が低い人は、他人にどう思われるかを常に気にしています。「嫌われたくない」「迷惑をかけたくない」と思うあまり、自分の意見や本音を抑えがちです。
結果として、次のようなことが起きやすくなります。
- いつも相手に合わせすぎてしまう
- ノーと言えず、無理なお願いを断れない
- 自分を偽ってまで良い人を演じてしまう
こうした行動は、一時的には円満な関係を保てるかもしれませんが、長期的には心が疲弊してしまいます。
また、「本当の自分を理解してもらえていない」という孤独感や疎外感にもつながりやすいのです。
さらに、相手に依存的になりすぎたり、少しのことで不安になったりと、人間関係全体が不安定になりやすいのも特徴です。
「きっと嫌われた」「あの言葉は自分を否定している」など、相手の言動をネガティブに受け取るクセも、トラブルの原因になることがあります。
仕事や学校で本来の力が出せない
自己肯定感が低いと、自分の能力や価値を信じられないため、積極的な行動が取りにくくなります。特に、次のような場面でその影響が出やすくなります。
- プレゼンや会議で意見を言えない
- 新しい仕事や役割にチャレンジできない
- 失敗を恐れて行動が消極的になる
「どうせ自分なんて…」「失敗したらどうしよう」という思考が先行し、挑戦する前に諦めてしまうのです。
その結果、本来ならもっと評価されるはずのチャンスを逃してしまうことも少なくありません。
また、ミスをしたときも必要以上に自分を責めてしまい、次に活かす前向きな気持ちになれないのも自己肯定感が低い人の特徴です。
結果的に仕事や学業のパフォーマンスが下がり、ますます自信を失うという悪循環に陥ってしまいます。
このように、自己肯定感の低さは人との関わりや社会生活に大きな影響を与えます。
ですが、意識と行動を少しずつ変えていけば、こうした問題は必ず改善していきます。
次の章では、実際に私が取り組んだ改善方法を具体的にご紹介します。
私が実践した自己肯定感を高める5つの習慣

自己肯定感が低いことで悩んでいた私は、さまざまな方法を試しました。
その中で、特に効果を感じたのがこれから紹介する5つの習慣です。どれも特別なスキルやお金は必要ありません。
日常生活の中で意識を少し変えるだけで、確実に「自分を認める力」が育っていきました。では順にご紹介します。
1. 小さな成功体験を毎日記録する
自己肯定感が低いと、失敗やできなかったことばかりに目が向きがちです。そこで私は、逆に「今日できたこと」を意識して記録するようにしました。
- 朝きちんと起きられた
- 期限内に書類を提出した
- 人に笑顔で挨拶できた
このように些細なことでも構いません。
1日の終わりに振り返り、「今日も自分なりに頑張れた」と実感することで、自分への信頼感が少しずつ育ちました。
2. ネガティブな言葉を使わない
普段から「どうせ無理」「自分にはできない」といったネガティブな言葉を口にしていた私は、これを前向きな言葉に言い換えるように意識しました。
- 「失敗した」→「良い経験になった」
- 「無理だ」→「まずはやってみよう」
言葉が変わると、考え方も変わります。最初は意識しないと難しかったですが、習慣化することで自然とポジティブな思考が増えていきました。
3. ありがとう日記をつける
毎晩寝る前に、その日感謝したいことを3つ書き出しました。
- 美味しいご飯を食べられた
- 友人から優しい言葉をかけてもらえた
- 天気が良く気持ちよく過ごせた
この習慣を続けることで、日常の中にある「当たり前の幸せ」に気づけるようになり、自然と心が穏やかになりました。
感謝の気持ちを持つことで、自分や周囲に対する見方も優しく変わっていったのです。
4. 自分を褒める時間を持つ
一日の終わりに、自分をねぎらう言葉をかける時間を作りました。
- 「今日もよく頑張ったね」
- 「疲れたけどちゃんとやり切った」
最初は少し気恥ずかしさもありましたが、続けるうちに「完璧じゃなくても大丈夫」と思えるようになり、自己否定が和らいでいきました。
5. 適度な運動を習慣化する
心と体はつながっています。私はウォーキングやストレッチを日課にすることで、気分が前向きになり、ストレス耐性が上がるのを実感しました。
体を動かすことで、ネガティブな思考がリセットされ、「また明日も頑張ろう」という気持ちが自然と生まれたのです。
以上の5つの習慣は、どれもすぐに始められるものばかりです。
一気に完璧を目指すのではなく、できることから少しずつ取り入れることで、自然と自己肯定感は高まっていきます。
私自身が実感したように、「変われる自分」を信じて、一歩ずつ進んでみてください。
自己肯定感チェックリスト
自己肯定感が低いといっても、普段は自覚しづらいものです。
「私はどうなんだろう?」と気になった方は、まずは以下の簡単なチェックリストでご自身の傾向を確認してみましょう。
あてはまる項目が多いほど、自己肯定感が低くなっている可能性があります。
自己肯定感セルフチェック
- 失敗やミスを引きずり、自分を責めてしまう
- 他人と自分を比べて落ち込むことが多い
- 褒められても「そんなことない」と否定してしまう
- 何か新しいことに挑戦するのが怖い
- 自分の意見や気持ちを素直に表現できない
- 人に認められないと不安を感じる
- できていない部分ばかりに目が向いてしまう
- 「どうせ自分なんて」と思うことがある
いかがでしたか?
3つ以上あてはまる場合は、自己肯定感が低めの可能性があります。ただし、あくまで目安ですので「私はダメだ…」と落ち込む必要はありません。
まずは今の自分を知ることが、改善の第一歩です。
チェックを通して見えてくること
自己肯定感が低い人は、「できていない自分」にばかり意識が向きがちです。
その結果、自信を持つことが難しくなり、生活全体に消極的な影響が出てしまいます。
ですが、裏を返せば「自己肯定感を高める伸びしろ」がたくさんあるとも言えます。
今回のチェックであてはまる項目が多くても、落ち込まずに「これから少しずつ変えていこう」という前向きな気持ちを持つことが大切です。
この記事で紹介している習慣を取り入れながら、焦らず一歩ずつ進んでいきましょう。
自己肯定感が低い自分と上手に付き合うコツ

自己肯定感を高める努力をしていても、すぐに劇的に変わるわけではありません。
「自己肯定感が低いままの自分」とどう付き合っていくかも、同じくらい大切なポイントです。ここでは、無理なく前向きに過ごすためのコツをお伝えします。
無理に自己肯定感を高めようとしない
自己肯定感が低いと、「もっと自信を持たなきゃ」「ポジティブにならないと」と自分を追い込んでしまうことがあります。
しかし、こうした「○○すべき」という考え方こそが、さらに自分を苦しめてしまう原因にもなります。
大切なのは、今の自分を無理に変えようとしないこと。
「自己肯定感が低くても、私は私」と受け入れることが、結果的に心をラクにし、自然体でいられる第一歩になります。
低いままでもOKと認める
自己肯定感は、日によって高くなったり低くなったりするものです。ずっと高い状態を維持するのは、誰にとっても難しいこと。
だからこそ、「自己肯定感が低いときもあって当然」と考えるようにしましょう。
たとえば…
- 「今日はちょっと落ち込みやすい日だな」と認める
- 「自信がない自分も、今はそういう時期」と受け入れる
このように、否定せず優しく自分を見守る姿勢が、結果的に自己肯定感を育むことにつながります。
小さな喜びや自分の良いところに目を向ける
自己肯定感が低いときほど、「自分には良いところなんてない」と思い込みやすくなります。そんな時こそ、意識的に小さな喜びや良い部分に目を向けてみましょう。
- 美味しいご飯を食べられた
- 友達や家族と楽しい会話ができた
- 忙しい中でも少し休む時間が取れた
このような「小さなできたこと」を見つけることは、自分を認める練習にもなります。続けるうちに、「意外と悪くないかも」と思える瞬間が増えていきます。
焦らず、少しずつ進めば大丈夫
自己肯定感を育てるのは、一朝一夕ではありません。
他人と比べず、昨日の自分よりほんの少しだけ前に進んだことを喜ぶ気持ちが大切です。
落ち込む日もありますし、後戻りする日もあるでしょう。
それでも「ゆっくりでいい」「立ち止まってもいい」と自分に優しくすることで、自己肯定感は確実に少しずつ高まっていきます。
このように、「自己肯定感が低いままの自分」と上手に付き合いながら生きていく方法を知ることは、とても心をラクにしてくれます。
無理に変わろうとせず、今の自分を認めることから、自己肯定感アップは始まります。
まとめ

自己肯定感が低いことで、「どうせ自分なんて」「何をやってもうまくいかない」と感じてしまうことは、決して珍しいことではありません。むしろ、多くの人がこうした気持ちに悩み、時に前に進めなくなってしまうものです。かつての私も、まさにその一人でした。
ですが、この記事で紹介したような小さな習慣を日々の生活に取り入れていくことで、少しずつ心は変わっていきます。
毎日の小さな成功を意識すること。
ネガティブな言葉をポジティブに言い換えること。
感謝の気持ちを言葉にすること。
自分をねぎらう時間を持つこと。
体を動かして心を整えること。
これらはどれも特別なことではありません。それでも、続けていくうちに、「自分もなかなかやるじゃないか」「悪くないかも」と思える瞬間が必ず増えていきます。
また、自己肯定感は無理に高めようとしなくても大丈夫です。低いままの自分を受け入れ、「今の私でいい」と思えることも、立派な成長です。焦らず、自分のペースで少しずつ進めていきましょう。
最後に、この記事でお伝えした方法が、今のあなたの不安や悩みを軽くし、これからの毎日をほんの少しでも前向きにするヒントになれば嬉しいです。
あなたはもう、変わり始めています。
どうか、自分を大切にしてあげてください。
-
-
すぐ落ち込む私が見つけた“心がラクになる習慣”
ちょっとした一言で落ち込んでしまう。そんな自分がずっと嫌いでした。でもあるとき、「無理に強くならなくてもいい」と思えるようになってから、心が少しずつラクになったんです。 この記事では、私が実際に試して ...
-
-
「繊細で疲れる毎日」を変える3つの方法
「人よりすぐ疲れるのは、私が繊細すぎるから?」そんなふうに感じているあなたへ。実はその“疲れやすさ”、HSPなど繊細な気質と関係があるかもしれません。毎日の中で知らず知らずのうちに心と体のエネルギーを ...
-
-
【注目】繊細な人が「仕事が続かない」3つの理由とは
「仕事が続かない私は、どこかおかしいのかな…?」そんなふうに悩んでいるあなたへ。実は、繊細な気質(HSP)ゆえに、環境や人間関係に強いストレスを感じやすい人は少なくありません。 この記事では、仕事が続 ...
-
-
普通じゃなくていい。HSPが楽になる考え方
「なんで私は、普通にできないんだろう」そんなふうに自分を責めていませんか? HSPは、音や人の気配に敏感で、他人の気持ちを察しすぎるあまり、生きづらさを抱えやすい気質です。そして多くのHSPが、「せめ ...
-
-
HSP男子がたどり着いた“考えない時間”の作り方
私は昔から、何かあるとすぐ「どうしよう」「あのときの言い方、変だったかな」と頭の中でぐるぐる考えてしまうタイプでした。人間関係でも仕事でも、「あのときこう言えばよかった…」と夜眠れなくなることも多々。 ...