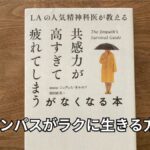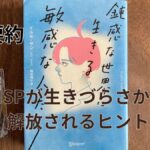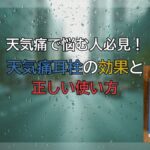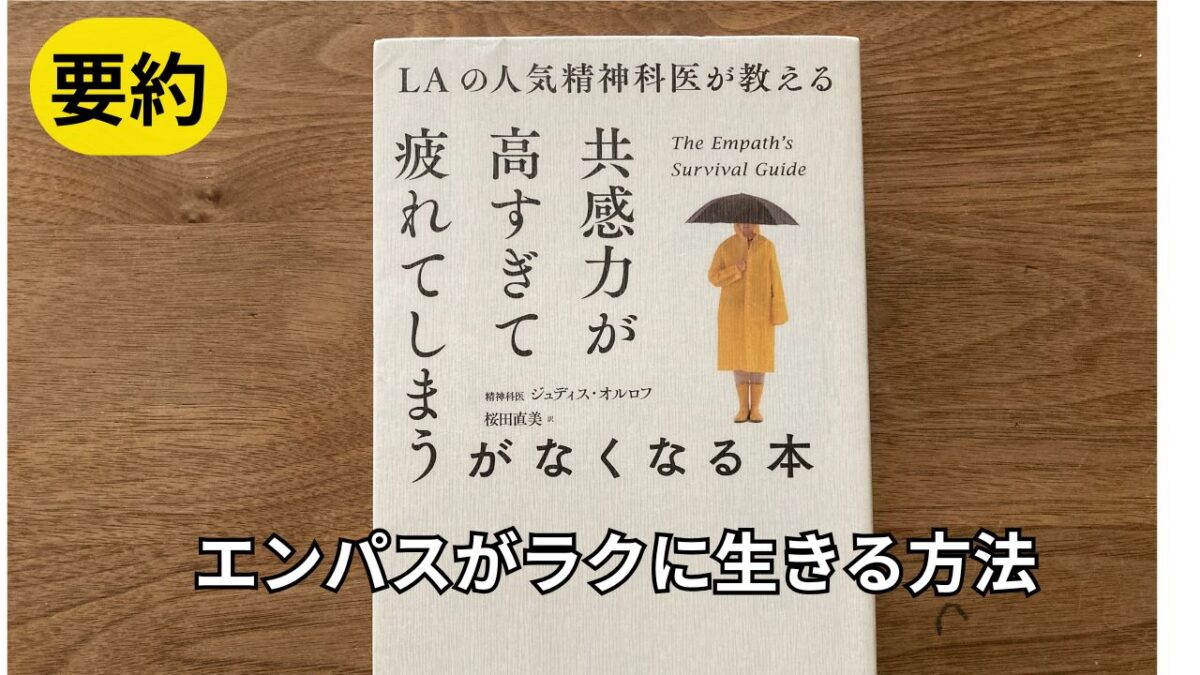
誰もが生まれながらにもっている共感力は
人間のすべての資質の中でもっとも貴重なものだ ーダライ・ラマ14世
「なぜ私はこんなにも疲れてしまうのだろう?」「人の気持ちに敏感すぎるのは、私の弱さ?」——そんなふうに悩んでいる人にこそ読んでほしいのが、LAの精神科医であるジュディス・オルロフ医師による『共感力が高すぎて疲れてしまうがなくなる本』です。
この本では、共感力の高さが生まれつきの気質である「エンパス」という存在として解説されており、「気にしすぎ」「神経質」と言われて傷ついてきた人に、まったく新しい視点を与えてくれます。
著者自身もエンパスであり、精神科医として多くのエンパスを診てきた経験をもとに書かれた内容は、どれも具体的でリアル。「共感する力が強い人」は、他人の感情やエネルギーを吸収しやすく、それが無意識のうちにストレスになっているという仕組みを、わかりやすく教えてくれます。
また、単に「感受性が強い人」として片づけられがちな特徴に、科学的・心理学的な根拠があることを知ることで、「自分は変じゃなかった」と安心する人も多いはず。
まさに繊細さを肯定し、共感力を武器に変えるためのガイドブックといえる一冊です。
エンパスという存在を知って救われた
この本を読んで初めて、「HSP(ハイリー・センシティブ・パーソン)」よりもさらに繊細な気質として「エンパス」という言葉を知った、という方も多いのではないでしょうか。私自身もその一人です。
エンパスとは、他人の感情や体調、エネルギーを無意識に受け取ってしまうほど、共感力が極めて高い人のこと。
HSPと混同されやすいですが、HSPが「感受性の強い人」であるのに対し、エンパスは“相手の感情や痛みを自分のことのように感じ取ってしまう”という特徴があります。
エンパスの特徴チェックリスト(本書より一部抜粋)
以下は本書に掲載されている「自己診断リスト」の一部です。これに16個以上当てはまると、完全なエンパスと判断されるとされています。
| チェック項目 | 内容 |
|---|---|
| ✔️ 人混みにいるとすぐに疲れる | 特に電車やショッピングモールなど |
| ✔️ 感情の起伏が激しい人に会うと消耗する | 相手の感情に巻き込まれてしまう |
| ✔️ 動物や自然と強くつながっていると感じる | 特に動物の感情に敏感 |
| ✔️ 誰かの悲しみが自分のことのように感じられる | 映画やニュースでも強く影響を受ける |
| ✔️ ひとりの時間がないと心がしんどい | 他人のエネルギーにさらされる時間が長いと消耗する |
私の場合、このリストの20項目中、19個が当てはまりました。
それを知ったとき、まるで霧が晴れるような感覚がありました。「ずっと違和感を感じてきたけど、実はエンパスだったのか」と思えた瞬間、小さいころから感じていたモヤモヤがすっと消えました。
エンパスを知ることは、自分を取り戻す第一歩
これまで「疲れやすい」「空気を読みすぎる」と感じていたのは、エンパスとしての資質だったと知ることで、初めて自己理解が深まりました。違和感の正体に名前がついたことで、強い安心感が生まれました。
他人と同じように生きられないのは、劣っているからではない。「ただ違うだけ」なのだと、ようやく納得できたのです。
知らないということは怖いことであり、知れば怖くなくなるのです。byまぬるん
エンパスにはタイプがある?あなたの中にある“繊細な力”

「エンパス」とひとくちに言っても、すべての人が同じ特徴を持つわけではありません。
著者ジュディス・オルロフ医師によれば、エンパスにはさまざまなタイプがあり、それぞれ異なる“受け取り方”をしています。
自分のタイプを知ることで、どんなときに疲れやすいのか、どう対処すべきかが見えてきます。
以下は、本書で紹介されている主なエンパスタイプの一覧です。
主なエンパスタイプ一覧(本書より)
| タイプ名 | 特徴 | あてはまる人の傾向 |
|---|---|---|
| 感情エンパス | 他人の感情をそのまま受け取ってしまう | 喜怒哀楽に巻き込まれやすい |
| 身体エンパス | 他人の体調や痛みを感じる | 近くの人の頭痛が自分にも伝染することも |
| 直感エンパス | 言葉よりも“空気”で物事を察知する | 場のエネルギーや未来の気配を感じる |
| 予知エンパス | 未来の出来事を事前に察知することがある | デジャヴ体験が多い/夢で未来を感じる |
| 地球エンパス | 地震や気候変動に敏感に反応する | 台風前に体調を崩すことがある |
| 動物エンパス | 動物の気持ちを深く読み取る | ペットと深い絆を持つ人によく見られる |
| 植物エンパス | 植物のエネルギーと共鳴しやすい | 自然と共にある暮らしに安心感を感じる |
私自身、この分類を知って「まさにこれだ!」と感じたことがいくつもありました。
特に直感エンパスの中でも、予知エンパス・地球エンパス・動物エンパスの特性が強くあらわれていると感じています。
たとえば、予知夢を見る、台風が近づいてくるときに体調が悪くなる、猫の気持ちが何となくわかる、初対面の人の雰囲気から「この人とは相性が合う/合わない」が一瞬でわかる……といった体験は、ずっと不思議に思っていました。
でもこの本のおかげで、それが「繊細な力」の一種であり、自分の感性なのだと理解できたのです。
自分のタイプを知ることは、生きづらさを軽くする鍵
「なぜ自分はこんなに疲れるのか」「人と同じようにできないのか」——そんな問いに対して、この“エンパスタイプ”という視点は明確なヒントを与えてくれます。
自分に合った対処法や距離の取り方を知ることが、心を守る第一歩です。
共感疲労とバーンアウトの違い
「仕事がつらい」「人と関わるのがしんどい」——そんな感情の背景にあるのが、共感疲労やバーンアウト(燃え尽き症候群)です。
この二つは似ているようで、実は原因も対処法も異なります。
共感疲労とは?
共感疲労(エンパシー・ファティーグ)とは、他人の苦しみや感情を過剰に取り込むことで、精神的に疲弊してしまう状態を指します。
特にHSPやエンパスの人は、相手の感情を自分のことのように感じ取ってしまうため、日常的な人間関係でも強いストレスを感じやすいのが特徴です。
✔ 他人の悲しみを見聞きするだけで涙が出る
✔ 誰かの怒りに直面すると、自分も苦しくなる
✔ 人の相談を聞いたあと、ぐったりしてしまう
このような経験が多い人は、共感疲労に陥っている可能性があります。
バーンアウトとは?
一方、バーンアウト(燃え尽き症候群)は、長期間にわたる過度なストレスや責任感から、心と体が限界を迎えてしまう状態です。
特に医療・福祉・教育など「人のために働く職業」に多く見られます。
✔ やる気がまったく起きない
✔ 朝起きた時からすでに疲れている
✔ 仕事中に無気力・無感動になる
バーンアウトは「意欲の喪失」が中心であり、共感疲労よりも職業的ストレスの蓄積が主因となります。
違いをまとめると…
| 比較項目 | 共感疲労 | バーンアウト |
|---|---|---|
| 原因 | 他人の感情を過剰に受け取る | 長時間の過労やストレス |
| 対象 | 対人関係・感情のやりとり | 仕事全般・責任感 |
| 主な症状 | 感情の消耗、過剰な気遣い、疲労感 | 無気力、うつ状態、やる気の消失 |
| 主な対処法 | 感情の境界線を引く・セルフケア | 休養・職場環境の見直し・相談 |
共感疲労はエンパスの宿命ではない
本書では、「共感力が高いからこそ疲れやすい。
でも、だからといってそれに飲み込まれる必要はない」と繰り返し語られています。
共感力は弱さではなく、強さ。ただし、それを生かすには「距離感」や「エネルギーの回復」が不可欠です。
「私は変じゃなかった」——他人軸から自分軸へ戻るヒント

この本を読んで、何よりも心が救われたのは、「私は変な人じゃなかったんだ」と思えたことです。
小さなころから「人の顔色を見すぎる」「空気を読みすぎる」「すぐに疲れる」ことが多く、自分でも「生きづらい」と感じてきました。
でも、それは“欠点”ではなく、エンパスという特性だったのです。
他人の感情を背負いすぎていた私
- 他人が不機嫌だと「私のせいかな?」と考えてしまう
- 困っている人がいると助けなきゃと思ってしまう
- 誰かが苦しんでいるのを見ると、何もできない自分に罪悪感を抱く
これらはすべて、共感力が高いからこその反応。
でもそれが積み重なると、自分の感情が見えなくなり、他人軸で生きてしまうことになります。
自分軸に戻るための3つのステップ
本書では、共感疲労を防ぐには「他人との間に健全な境界線を引くこと」が大切だと繰り返し述べられています。
ここでは、自分を守るためのヒントを3つ紹介します。
- 感情を自分と他人で分けて考える
→「これは私の感情?それとも相手の感情?」と立ち止まる習慣をつける。 - NOと言う練習をする
→ 頼まれごとにすぐ応じるのではなく、「今はできない」と言える勇気を持つ。 - 自分が落ち着ける空間や時間を確保する
→ 一人で散歩する、自然の中で深呼吸する、スマホを手放す時間をつくる。
「違っていていい」——自分を許せた瞬間
他人と同じようにできなくても、それでいい。
“繊細すぎる私”は、弱いのではなく、感受性の幅が広いだけ。
そう思えるようになったとき、肩の力が抜けて、「今の自分で大丈夫」と安心できるようになりました。
この本がくれたのは、“変わる方法”ではなく、“そのままの自分を認める方法”だったのだと思います。
共感力を強みに変える5つのセルフケア術

共感力が高いことは、確かに「疲れやすさ」と紙一重です。
しかし本書では、それを「繊細すぎる弱さ」ではなく、「人間らしさの源」として捉え直し、上手に扱うことで“強み”にできると繰り返し語られています。
では、エンパスが自分を消耗させずに生きるためには、どのようなセルフケアが必要なのでしょうか?
エンパスにおすすめのセルフケア術
以下は、本書で紹介されている中でも特に実践しやすく、効果的とされる5つの方法です。
① 境界線を意識的に引く
- 相手の感情に巻き込まれないよう、「ここからは自分の領域」と線を引く
- たとえば、相手の怒りや悲しみを見聞きしたとき、「私はその感情を引き受けなくていい」と意識する
👉 心のフィルターを強化するイメージで、「今のは自分の感情じゃない」と唱える習慣を
② 一人で過ごす時間を“確保”ではなく“最優先”する
- 予定のない静かな時間を、スケジュールにあらかじめ確保しておく
- 誰にも気を遣わない時間が、心の回復に不可欠
👉 一人時間=自分を守るシールドと捉えよう
③ 自然とつながる習慣をもつ
- 緑の中で深呼吸をする
- 自然の水に触れる(海・川など)
- 植物や動物と触れ合う
👉 地球エンパス・動物エンパスの人には特に効果的
※HSPやエンパスには水に惹かれる方が多い(私も無性に海が見たい時がよくある)
④ センシングを遮断するアイテムを使う
- 音に敏感な人は耳栓やノイズキャンセリングヘッドホン
- 匂いや光が刺激になる人はアロマやアイマスク
👉 「疲れたら守る」ではなく、「疲れる前に守る」意識が大切
\私のおすすめ耳栓 会話はできるけど雑音だけシャットアウト/
⑤ 身体を通じて“グラウンディング”する
- 散歩、ヨガ、呼吸法などで「今ここ」に意識を戻す
- 地に足をつける感覚を得ることで、過剰な共感から切り離されやすくなる
👉 エネルギーが“自分の中心に戻る”のを感じることが目的
セルフケアは「甘え」ではなく「必要な戦略」
共感力が高い人ほど、他人を優先してしまい、自分を後回しにしがちです。しかし、自分のエネルギーを守ることは、誰かのために生きるためにも欠かせない準備です。
「頑張る」よりも「整える」ことを大切にして、自分にやさしい毎日を積み重ねていきましょう。
同じように悩んできた私から、読者へのメッセージ
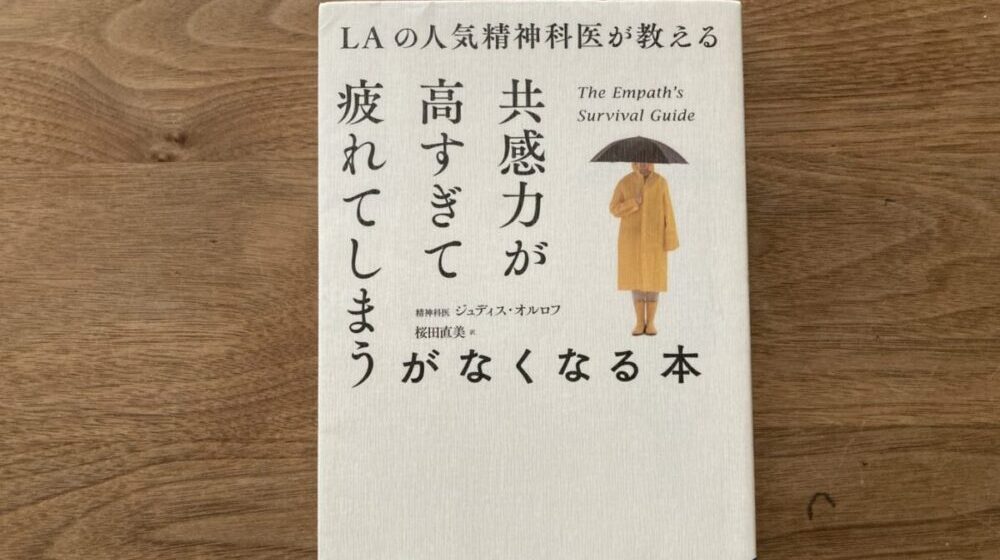
ここまで読んでくださったあなたは、きっと誰かの痛みに敏感で、空気を読むのが得意で、でもそのぶん「なんだかいつも疲れてしまう」と感じているのではないでしょうか。
私もずっとそうでした。
「気にしすぎ」「考えすぎ」「もっと図太くなれ」と言われるたびに、自分を責めて、どうにか“普通”になろうとしてきました。
でも、この本に出会って気づいたのです。私は“変な人”ではなく、“共感力の高い人”だったんだと。
そしてそれは、決して弱点なんかではなく、他の人にはない力でもあるということ。
誰かの気持ちに寄り添える力、空気の違和感を察知できる力、優しさを持ち続けられる力。
それは、これからの社会にこそ必要とされる繊細さなのではないかと思っています。
もしあなたがこんなふうに感じているなら…
- 人と会うたびにぐったりしてしまう
- 悩み相談をされることが多く、でも自分が苦しくなる
- 誰かが怒っていると、自分のことのように落ち込む
- 一人にならないと回復できない
- 自分だけが「生きづらい」と感じてしまう
そんなときは、「私はエンパスかもしれない」と立ち止まってみてください。
繊細さは、力に変えられる
エンパスは、何か特別な訓練でなれるものではなく、「もともとそういう感性を持っている人」です。
だからこそ、他人の痛みに寄り添いながらも、自分の境界線を守ることが必要なのだと思います。
私もまだ、うまく自分を守れない日があります。
でも、「自分はこのままでいい」と思えるようになっただけで、心がずっと軽くなりました。
あなたもきっと、大丈夫。
この本は、“あなたはあなたのままでいい”と、そっと背中を押してくれる本です。
まとめ|「共感力が高すぎて疲れてしまう」あなたへ贈りたい本
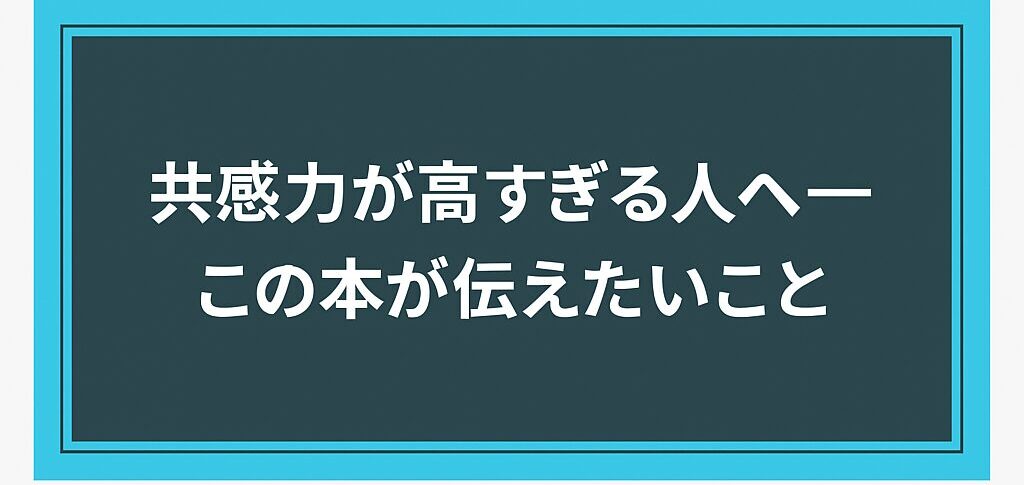
『LAの人気精神科医が教える 共感力が高すぎて疲れてしまうがなくなる本』は、HSPやエンパスといった繊細な気質を持つ人に向けて、「そのままのあなたでいい」と優しく語りかけてくれる一冊です。
この本のポイント
- エンパスとは?
HSPよりさらに繊細で、他人の感情やエネルギーを吸収しやすい気質。 - エンパスにはタイプがある
予知エンパス、地球エンパス、動物エンパスなど、自分に当てはまる特徴を知ることで対策が立てやすくなる。 - 共感疲労とバーンアウトは違う
共感疲労は感情の影響、バーンアウトは過労から来る無気力。どちらも早めのケアが大切。 - 自分軸に戻るヒント
「人にどう思われるか」より「自分がどう感じるか」に意識を向けよう。 - 共感力を強みに変えるセルフケア術
境界線、一人時間、自然とのつながりなど、エンパスに合った対処法を取り入れて。
繊細さは、隠すものではなく、大切に育てていくもの。
「自分はどうしてこんなに疲れるのか」と悩んでいる方にとって、この本は自分を知る“取扱説明書”のような存在になるはずです。
「共感力の高さ」が生きづらさになっているなら、この本はあなたの人生を変える一冊になるかもしれません。
ぜひ一度、読んでみてください。
-
-
名著『~共感力が高すぎて疲れてしまうがなくなる本』解説|エンパスの生き方
誰もが生まれながらにもっている共感力は人間のすべての資質の中でもっとも貴重なものだ ーダライ・ラマ14世 「なぜ私はこんなにも疲れてしまうのだろう?」「人の気 ...
-
-
ミニマリストの原点!『ぼくたちに、もうモノは必要ない。』要約と実践方法をわかりやすく解説
気づけば家の中はモノでいっぱい。片付けても片付けてもスッキリしない——そんな経験はありませんか? モノを持つことで安心したり、誰かと比べてしまったり…。しかし本当に豊かな暮らしは、「たくさん持つこと」 ...
-
-
「鈍感な世界に生きる敏感な人たち」要約|HSPが生きづらさから解放されるヒント
人付き合いや日々の出来事で「なんだか生きづらい」と感じたことはありませんか?私もずっとそうでした。人の言葉や表情に敏感すぎて疲れたり、表面的な会話に興味が持てなかったり…。自分は弱いのではないか、何か ...
-
-
『静かな人の戦略書』:内向型・HSPが自分らしく輝くための実践ガイド
「もっと積極的にしないと」「うまく話さなきゃ」。そんなふうに、自分を責めてしまうことはありませんか? 私自身、内向的で人前で話すのが苦手だったり、気を使いすぎて疲れることがよくあります。そんな私にとっ ...
-
-
天気痛で悩む人必見!天気痛耳栓の効果と正しい使い方
天気痛に悩まされ、毎日のように頭痛やめまいで憂鬱な気分になっていませんか? 私自身も長年、雨が降る前のズキズキする頭痛や、気圧が低下すると現れる肩こりやめまいに苦しんできました。 ある日、佐藤純医師監 ...