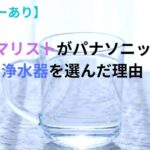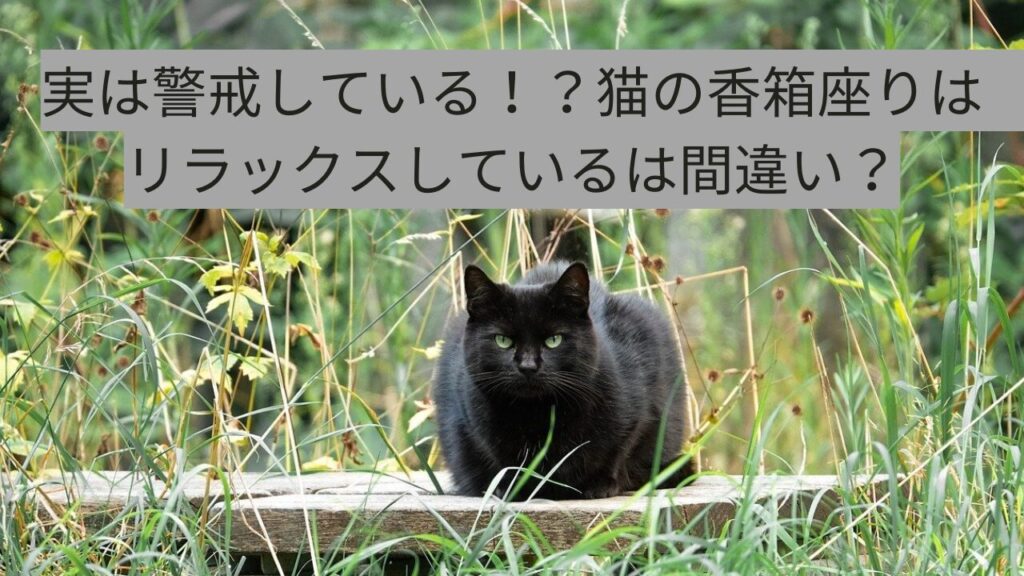

香箱座りをする猫ってかわいいですよね。でも香箱座りをする時の猫の気持ちって考えたことはありますか?
香箱座り(こうばこずわり)は、猫がリラックスしている時に見られるポーズとして知られていますが、実は「休憩しつつも、周囲を警戒している状態」なのです。
この記事では、香箱座りについて、名前の由来や香箱座りをする時の猫の心理について詳しく解説します。
香箱座りとは?

香箱座りは、猫が前足を胸の下に折りたたみ、後ろ足も曲げ、しっぽは身体に沿わして、まるで香箱(お香を入れる箱)のようにコンパクトに座る姿勢です。
作家の芥川龍之介が作品『老年』『お富の貞操』で猫が「香箱を作る」と表現しており、少なくとも1900年前後位からは、猫のこの姿が香箱に似ているという認識があったと考えられます。
ちなみに、英語では一斤まるまるのパン(loaf)にそっくりなことから”cat loaf”と呼ばれています。

実は警戒している?香箱座りの真実
香箱座りがリラックスしているか警戒しているかは猫の専門書でも意見が分かれているところです。
私は、頭を持ち上げている時の香箱座りは休憩しつつも猫が周囲を警戒し、素早く対応できる準備を整えた態勢だと考えます。
以下に理由を説明します。
香箱座りは前足を体の下にたたんでいるため、即座に動けると考えるのは難しいように思われますが、後ろ足は曲げているだけですぐに踏み込める状態ですし、前足も瞬時に地面に置き、動くことができます。
実際、私の経験でも、知らない猫に近づいた際に、瞬時に前足を地面に着けて警戒モードに切り替わり、さらに近づけば素早く逃げられることが何度もありました。

また、野生の鹿やうさぎ、ひつじも香箱座りをしており、この時は頭を持ち上げ、耳を立てて周囲を警戒しているのが分かります。


猫は元来、狩猟動物であり、外敵から身を守りながら休息する習性を持っています。
香箱座りは、その本能の一環であり、外敵にすぐ対応できるように準備を整えながら、休息を取るバランスの取れた姿勢と考えられます。
『ざんねんな生き物』シリーズで有名な動物学者の今泉忠明さん(ねこの博物館館長)監修の『ねこの事典』にも香箱座りについて「リラックスしているものの、少しだけ警戒している状態」と記載されています。

しかし、頭を床につけ、液体と化している場合は警戒をといて完全にリラックスしている状態といえます。(下の画像を参照)

香箱座りをする他の場合
頭を上げている時の香箱座りは休憩しつつも周囲を警戒している態勢ですが、他にも香箱座りをする場合があります。
精神を落ち着かせるため
イライラしている時や興奮状態を落ち着かせるためにも香箱座りをすることがあります。
これは自分を防御態勢(香箱座り)に置くことで、安心感を得ようとしていると考えられます。
寒い
単純に寒い時も香箱座りをします。
香箱座りは冷えやすい四肢やしっぽを身体に密着させますので、体温を効率的に保つことができます。
香箱座りと猫の気持ち

香箱座りをしている猫の気持ちとしては、リラックスしつつも、警戒心をといていないというのが妥当だと思います。
香箱座りをしている猫は一見、のんびりしているように見えても、すぐに動ける態勢を保ちながら、私たちの動きや周囲の音をしっかり感じ取っています。
やっぱり個体差はある

もちろん、猫には個体差がありますので、香箱座りをする猫しない猫、香箱座りをしていても完全にリラックスしてそのまま寝てしまう猫もいます。
また、上の写真のように前足を前にチョンと揃えて可愛らしく座る猫もいます。(スコティッシュはこの座り方が多いです。理由はコチラ)
香箱座りと健康との関係
健康な猫は自然に香箱座りを取ることができますが、関節や筋肉、内臓に問題がある場合、この姿勢を取ることが難しくなります。
特に高齢の猫や肥満の猫は、足を折りたたむことが困難になるため、香箱座りをしなくなることがあります。
もし、「最近香箱座りをしないな」と感じたら、健康チェックが必要です。
まとめ

香箱座りは、猫が周囲に適度な警戒心を持ちながらリラックスしている状態です。
リラックスしているように見えますが、猫はいつでも素早く動ける準備を整えています。
猫が香箱座りをしている時は、彼らが安心しつつも、状況に応じて反応できる態勢を取っていることを理解しましょう。
-
-
痩せ型必見!無理なく太るための高カロリー食材まとめ
私自身、長年痩せ型で悩んでいましたが、高カロリー食品を上手に取り入れることで、3ヶ月で5kgの増量に成功しました。 その経験をもとに、健康的に太るための高カロリー食材をお伝えします。 今すぐ食材をチェ ...
-
-
断捨離で得られるメリット5選!生活が変わる理由
以前の私は、物に囲まれた生活でストレスを感じていました。 しかし、断捨離を始めてから、心も体も軽くなり、生活が一変しました。 今回は、私が実感した断捨離の効果と、その方法についてご紹介します。 Con ...
-
-
「捨て活」は本当に効果があるのか?実際に捨てて感じたリアルな効果
私自身も最初は半信半疑でした。 しかし、佐々木典士さんの著書『ぼくたちにもうモノは必要ない』を読んで、思い切ってモノを捨て始めてみると、想像以上の変化が訪れました。 実際に捨て活を経験して得たリアルな ...
-
-
【レビューあり】ミニマリストがパナソニックの浄水器を選んだ理由
「できるだけ物を持たず、シンプルに暮らしたい」。 と考える人にとって、飲み水の確保は悩ましい問題です。 ペットボトルはゴミが増えるし、ウォーターサーバーはスペースを取る。 そこで私が選んだのが、パナソ ...
-
-
現代人に必要なのはTo Doじゃない。「やらないこと」をハッキリしよう
私たちは毎日、やるべきことに追われています。 To Doリストを作っては、こなせなかった自分に落ち込む。 そんな経験、ありませんか? でも本当に大事なのは、「やること」ではなく「やらないこと」を明確に ...
参考文献
・『ねこの事典』 今泉忠明監修
・『気持ちを知ればもっと好きになる!猫の教科書』 CAMP NYAN TOKYO監修
・『教養としての猫』 山本宗伸監修