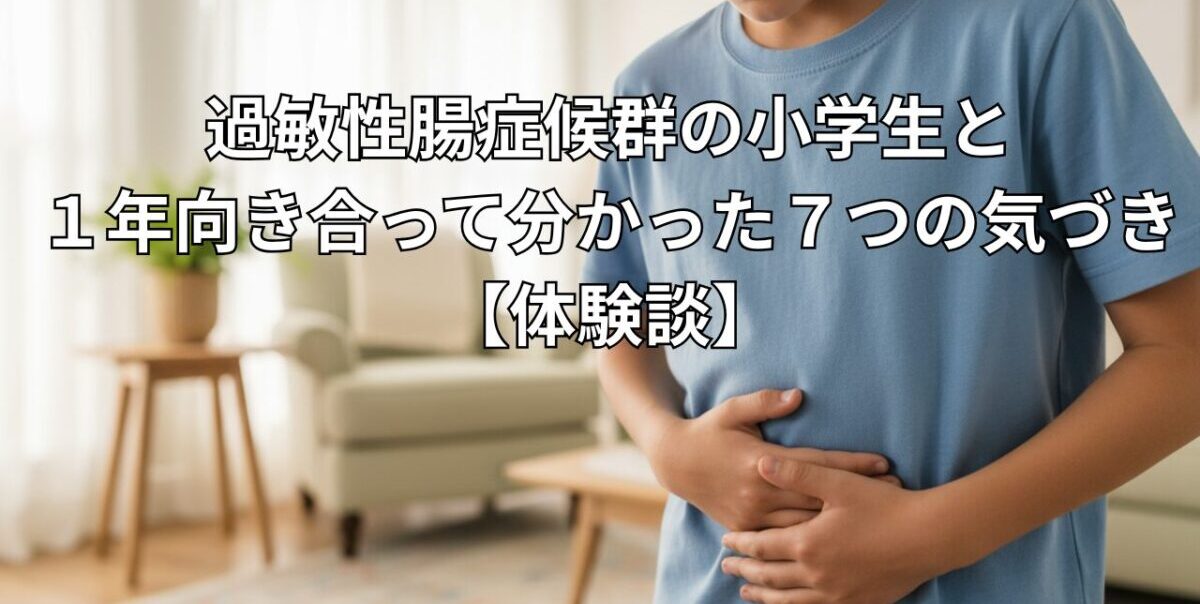
朝になると「お腹が痛い」と言って、学校に行けない。
でも、昼ごろにはケロッとしてゲームをしたり、宿題もこなせる。
病院で検査をしても「特に異常はありません」と言われてしまう。
小学生のお子さんがそんな状態だと、「本当に大丈夫なのか」「学校を休ませていいのか」と、親の心はずっと落ち着かないと思います。
私もまったく同じでした。
わが家の9歳の息子は、便秘型の過敏性腸症候群(IBS)の小学生です。
発症から1年あまり、何度も病院を回り、誤った診断を受けたあとで、ようやく大学病院の小児IBS専門医にたどり着きました。
この記事では、そんな「過敏性腸症候群の小学生」と1年向き合う中で、親として気づいたことを7つの視点からまとめています。
- 朝のお腹の痛みと学校の関係で感じたこと
- 検査で異常がなくても、子どもは本当に苦しんでいると分かったこと
- 薬や生活リズム、家族の関わり方で少しずつラクになってきたこと
- 親の声かけを変えることで、子どもの表情も変わっていったこと
同じようにお子さんの腹痛や登校について悩んでいる親御さんが、「うちだけじゃないんだ」と少しでも安心できるように書いていきます。
なお、ここに書く内容はあくまで一家庭の体験談です。
治療法や薬を勧めるものではありません。
お子さんの診断や治療については、必ずかかりつけ医と相談してください。
小学生の息子が「朝お腹が痛い」と言い出した日から診断まで
朝だけ強くなるお腹の痛みと、続く便秘
最初は、本当に「よくあるお腹の不調」だと思っていました。
ある朝、息子が布団の中でお腹を押さえながら「お腹が痛い…」と言い、その日は起き上がれず、小学校を休むことになりました。
ところが、その後も同じような日が続きます。
- 朝になるとお腹が痛くて起きられない
- ご飯もほとんど食べられず、昼過ぎまで寝ている
- 夕方になると元気になり、ゲームや宿題はこなせる
さらに、排便のペースも4〜5日に1回ほど。出るときはコロコロの硬い便で、ひどいときには肛門が切れてしまうこともありました。
「出ないとお腹がつらいのに、出たら出たで痛くて泣いてしまう」
そんな状態が続き、親としてどうしてあげればいいのか分からない日々でした。
体重が10%も減少
腹痛と便秘と吐き気が続き、子供の食欲がどんどん減っていき、体重が10%も減ってしまいました。
顔もみるみるげっそりしていき、好きな物を食べさせようとしてもあまり食べず、心配で身がちぎれるような思いをしました。
いろいろ調べて、体重を増やす高栄養のプロテインがあることを知り、それを飲ますことにしました。
すると、体重の減少は抑えられ、一安心しました。

学校の朝と雨の日に悪化する不思議さ
腹痛には、少しずつ「パターン」が見えてきました。
- 学校のある日の朝に特に痛みが強い
- 雨の日や天気が崩れる日は、さらに痛みがひどくなる
一方で、休日はそこまで強い腹痛が出ない日が多くありました。
息子は「学校には行きたい」と何度も言っていましたし、友だちとも仲が良いタイプです。
それでも毎朝のようにお腹を押さえて苦しそうにしている姿を見ると、
- 本当に体の病気なのか
- それとも学校のストレスなのか
親の側も受け止め方に迷い、心が揺れる時期が続きました。
いくつもの病院を回り、ようやくたどり着いた「過敏性腸症候群」という診断
腹痛と便秘が続くため、私たちは近所の小児科だけでなく、別のクリニックや病院も受診しました。
レントゲンや腹部エコー、浣腸、点滴など、息子の身体にはいろいろな検査や処置が行われましたが、決定的な原因はなかなか見つかりません。
一時期は、腹部エコーの結果から「上腸間膜動脈症候群かもしれない」と言われたこともあります。
しかし、1ヶ月半ほどこの病気の対策をとっても全く改善しなかったことから、私の中には違和感が残りました。
そこで、私たちは自分でも情報を集めながら、セカンドオピニオンをお願いすることにしました。
最終的に紹介されたのが、大学病院の小児科にいる小児IBS(過敏性腸症候群)の専門医です。
これまでの経過を丁寧に聞いたうえで、先生はこう伝えてくれました。
「お子さんの症状は、小児の過敏性腸症候群(IBS)と考えられます。
命に関わるような重い病気ではありませんが、時間をかけて付き合っていく必要があります。」
そのとき私の中には、
- 大きな病気ではなさそうだという安心感
- すぐに治るわけではないという不安
が同時にありました。
それでも、「病名がついた」「この症状には名前がある」と分かったことで、息子の「お腹が痛い」という訴えを、ようやく心から信じてあげられるようになったと思います。
過敏性腸症候群の小学生と1年向き合って分かった7つの気づき
【気づき①】検査で異常がなくても、子どもの「痛い」は本物だった
検査は「異常なし」でも、毎朝の腹痛は続いていた
レントゲンや血液検査、エコーをしても「大きな異常はありません」と言われることが続きました。
それでも家では、朝になるとお腹を押さえて動けない息子がいます。
検査結果だけを見ると「大丈夫」と言われているように感じますが、目の前の子どもは明らかにしんどそうです。
このギャップの中で、正直なところ私の心には
- 「本当にそんなに痛いのかな?」
- 「学校に行きたくない気持ちもあるのかな?」
という疑いも生まれていました。
大学病院で過敏性腸症候群(IBS)と診断され、「検査には映らないタイプの不調です」と説明を受けたとき、
やっと「息子の『痛い』はずっと本物だった」と素直に受け止められました。
これが、最初の大きな気づきでした。
【気づき②】「朝」と「学校」がキーワードになる腹痛だった
朝に強く出て、昼から元気になる不思議なリズム
息子の腹痛は、一日中続くわけではありませんでした。
- 朝は強い腹痛で起き上がれない
- 昼過ぎから少しずつマシになってくる
- 夕方には、ゲームもできるし宿題もこなせる
このパターンだけを見ると、親としては
「本当に病気なのかな」と迷いが生まれます。
IBSについて調べるうちに、「登校前の朝に強く出る腹痛」は、子どもの過敏性腸症候群でよく見られると知りました。
「朝だからサボりたい」のではなく、「朝が一番つらい病気」なのだと分かってから、息子の状態の見え方が変わりました。
「学校には行きたいのに行けない」息子の気持ち
息子は、友だちや学校が好きなタイプです。
本人も「学校には行きたい。でもお腹が痛い」と何度も口にしていました。
- 行きたくないから休むのではなく
- 行きたいのに、身体がついてこない
この状態は、親が思っている以上に子どもにとってつらいのだと思います。
登校をしぶっているのではなく、過敏性腸症候群で朝が特につらいとして見られるようになったことも、大きな気づきでした。
【気づき③】薬で「出る」ようになっても、腹痛はすぐゼロにはならない
モビコールで排便は改善したけれど
現在、息子はモビコールという慢性便秘症の治療薬などを処方されています。
飲み始めてから、2日に1回は便が出るようになりました。
発症直後の「4〜5日に1回」「肛門が切れるほどの硬い便」と比べると、これは大きな変化です。
しかし、排便が整っても、朝の腹痛はすぐには消えませんでした。
「こんなに出るようになったのに、どうしてまだ痛いんだろう?」
親としては、別の不安が生まれてきます。
「良くなっているのか不安」という親の気持ち
IBSは「便秘を治せば終わり」という単純な病気ではないと分かってきました。
腸だけでなく、自律神経やストレスとの関係も深く、良い日と悪い日を行き来しながら、少しずつ波が小さくなっていく病気なのだと思います。
「薬を飲んでいても波があるのは普通」と考えられるようになってから、親としての不安も、少しだけ落ち着きました。
【気づき④】生活リズムとルーティンが、心と体の土台になる
朝のルーティンで自律神経を意識するようになった
息子のIBSには、自律神経も関わっているかもしれないと言われました。
そこから意識し始めたのが、生活リズムと毎日のルーティンです。
わが家では今、
- 朝起きたらカーテンを開けて日光を浴びる
- コップ一杯の水を飲む
- 痛みが強い日は、朝ごはんは温かいスープだけでも飲む
という流れを大切にしています。
どれも特別なことではありませんが、毎日同じことをすることで、息子の体も心も、少しずつ落ち着いてきたように感じます。
夜のストレッチと「猫のクッション」がくれる安心感
夜は21時に就寝・7時に起床を基本にし、寝る前に家族でストレッチをしています。
YouTubeの「便秘解消ストレッチ」「自律神経を整えるストレッチ」を見ながら、みんなで体を伸ばす時間は、親子のコミュニケーションにもなりました。
また、息子は猫のクッションが大好きで、横になるときや寝るときはそのクッションを抱いています。
ストレッチと猫のクッションは、息子にとって「これをしていれば少し安心できる」お守りのような存在になっています。
【気づき⑤】学校と細かく連携すると、「行きたい気持ち」を守りやすい
アプリでその日の状況を伝えるようにしたこと
わが家では、朝お腹が痛い日は学校の連絡アプリを使って、
「腹痛が治り次第、登校します」
と伝えるようにしています。
これによって、
- 親も「無理に今すぐ行かせなくていい」と思える
- 先生も「今日はこういう状況なんだ」と分かる
という状態になり、その日のベストを一緒に探せるようになりました。
体育をその日の体調で決めてもらえる安心感
担任の先生にはIBSのことや病院での経過も伝えています。
体育の授業では、毎回「今日はできそう?」と声をかけてくれ、息子の体調に合わせて参加したり見学したりしています。
「体育はがんばって出なきゃいけないもの」から「その日の体調で決めていいもの」に変わったことで、
息子にとって学校が少し安心できる場所になったと感じます。
友だちに手を引かれた一場面から学んだこと
ある日、途中から息子を学校に送っていったときのことです。
ちょうどクラスの子どもたちが体育で外に出てきて、「〇〇くんや!」「今から体育やで」「一緒に着替えよ!」と言いながら、
息子の手を握って教室へ走っていきました。
その姿を見て、私はとても救われる思いがしました。
- クラスの子たちは、息子を「病気の子」としてだけ見ているわけではない
- 一緒に遊ぶ仲間として受け入れてくれている
この一場面は、「学校と友だちの存在は、子どもの大きな支えになる」という気づきをくれました。
【気づき⑥】「学校がイヤなんでしょ?」と決めつけないことが大事だった
何度も「イヤなことない?」と聞いてしまった反省
IBSと診断される前、私は息子に何度もこう聞いていました。
- 「学校でイヤなことない?」
- 「先生や友だちに何か言われた?」
息子はそのたびに「ない」と答えますが、私はどこかで「本当は何かあるのでは」と疑っていました。
今振り返ると、この聞き方は「あなたは学校がイヤなんでしょう?」と決めつけているようなものだったと思います。
聞くのをやめたら見えてきた、息子の本当の表情
IBSという診断がつき、息子の腹痛に病名がついてからは、この質問をやめるようにしました。
代わりに、
- 「今日はどのくらい痛い?」
- 「行けそうだったら一緒に考えようか」
と、今の状態を一緒に確認する声かけに変えました。
すると、息子の表情が少し柔らかくなり、「学校には行きたいけどお腹が痛い」と、自分の気持ちを素直に話してくれるようになりました。
「学校がイヤなんでしょ?」ではなく、「どうしたら少しでも行きやすくなるかな?」と一緒に考えることが、子どもの安心につながるのだと感じています。
【気づき⑦】親が不安でも、情報と体験談があれば子どもを安心させられる
「重い病気ではない」と知ったときの安堵
最初の半年は、「もしかして大きな病気だったらどうしよう」という不安でいっぱいでした。
大学病院で「命に関わるような重い病気ではありません」と聞いたとき、正直ほっとしました。
もちろんIBSはつらい症状がありますし、すぐに治るものではありません。
それでも、
- 病名が分かったこと
- どう付き合っていけばいいか一緒に考えてくれる専門医がいること
この2つは、親として大きな支えになりました。
親が落ち着くと、子どもも少しずつ落ち着いていく
IBSについて本やサイトで情報を集め、他のご家庭の体験談も読むようになりました。
「うちだけじゃないんだ」と分かることで、私自身の不安が少しずつ和らいでいきました。
不思議なもので、親の表情が落ち着いてくると、子どもの表情も少しずつ変わってきます。
過敏性腸症候群は、すぐに完治を目指すというより、病気と付き合いながら「この子なりのペースで毎日を過ごせるようにする病気」だと受け止められるようになってきました。
過敏性腸症候群の小学生と暮らす、わが家の1日の流れ
朝:起きられない日と登校できる日の分かれ目
息子の1日は、まず「朝にどれくらいお腹が痛いか」で大きく変わります。
朝7時ごろに声をかけて起こし、カーテンを開けて日光を入れます。
その時点でスッと起きられる日もあれば、布団の中でうずくまって「今日はちょっと無理かも」と言う日もあります。
わが家では、こちらが一方的に決めるのではなく、
- 「今日はどれくらい痛い?」
- 「少し休んだら行けそう? それとも今日は様子を見ようか?」
と、必ず本人に確認してから登校するかどうかを一緒に判断しています。
お腹が痛い日は、朝ごはんをしっかり食べることは難しいので、温かいスープや飲みやすいものを少しだけでも口にしてもらうようにしています。
そのうえで、「腹痛が治り次第登校します」と学校のアプリで連絡を入れ、布団で休む時間をとります。
昼〜夕方:休む日の過ごし方と「元気になってくる時間帯」
お腹の痛みが強い日は、お昼ごろまでほとんど横になって過ごします。
この時間帯は、勉強をさせるよりも、とにかく体を休めることを優先しています。
とはいえ、ずっと何もせずにいるわけではなく、
- 横になりながらYouTubeの教育系チャンネルやテレビの教育番組を見る
- 図書館から大量に借りてきた本を読む
- 勉強や読書に疲れたらゲームを少しだけする
といった過ごし方をしています。
毎回のように、夕方になると少しずつ元気が戻ってくるのが息子の特徴です。
表情が明るくなってきた頃合いを見て、学校から出ている宿題に取り組みます。
その日の体調にもよりますが、「できる範囲でやればいい」というスタンスにして、全部こなせなかったとしても責めないように気をつけています。
親としては「勉強が遅れるのでは」と心配になることもありますが、今は「まず体調を整えること」が優先だと自分に言い聞かせるようにしています。
夜:ストレッチと早めの就寝でリズムを整える
夜は、できるだけ21時には寝ることを目標にしています。
就寝前には、家族みんなでストレッチをするのが日課です。
- 便秘解消ストレッチ
- 自律神経を整えるストレッチ
などの動画を一緒に見ながら、親子で体をゆっくり動かします。
これは、単に体のためだけでなく、「一日お疲れさま」と気持ちを共有する時間にもなっています。
息子は、寝るときやしんどいときには必ずお気に入りの猫のクッションを抱きます。
そのクッションがあるだけで安心するようで、
布団に入ってからも落ち着いて眠りにつきやすくなりました。
こうして、
- 朝は日光と水で体を起こす
- 昼は無理をさせず休ませる
- 夕方から少しずつ勉強や遊びを戻す
- 夜はストレッチと早めの就寝でリズムを整える
という流れを続けることで、IBSと付き合いながらも、「息子なりの1日」を一緒に形にしている感覚があります。
親として「やめてよかったこと」と「続けてよかったこと」
やめてよかった声かけ:「学校がイヤなんでしょ?」と決めつけること
IBSと診断される前、私は息子に何度もこう聞いていました。
- 「学校でイヤなことないの?」
- 「先生に何か言われた?」
- 「友だちとケンカしてない?」
息子はそのたびに「ないよ」と答えます。
それでも私は、心のどこかで「本当は何かあるんじゃないか」と疑っていました。
今振り返ると、この聞き方は
- 「あなたは学校がイヤなんでしょ?」
- 「どこかに“イヤな理由”があるはずだ」
と、決めつけているようなものだったと思います。
息子からすれば、
- 本当にお腹が痛い
- 学校には行きたい
- でも、親からは「イヤなことがあるんでしょ?」と何度も聞かれる
これはかなりしんどい状況だったはずです。
IBSと診断され、「これは検査には映らないけれど、実際にある不調なんです」と説明を受けてから、私はこの質問をやめました。
代わりにするようにしたのは、
- 「今日はどのくらいしんどい?」
- 「どこが一番つらい?」
- 「行けそうだったら何時間目からにする?」
といった、“今の状態”を一緒に確認する声かけです。
すると、息子の表情が少し柔らかくなり、
「本当は行きたいんだけどね」「今日は3時間目からなら行けそう」
と、自分の気持ちや希望を前よりも素直に話してくれるようになりました。
「学校がイヤなんでしょ?」をやめたことは、親として本当に良かったと思っていることの一つです。
続けてよかった習慣:家族みんなでストレッチをする時間
もう一つ、「続けてよかった」と感じているのが、家族でのストレッチです。
IBSには自律神経も関係しているかもしれないと聞いてから、寝る前にYouTubeの
- 便秘解消ストレッチ
- 自律神経を整えるストレッチ
などの動画を見ながら、家族全員で体を伸ばすようになりました。
もちろん、ストレッチだけで全部が良くなるわけではありません。
それでも、この時間にはいくつかの意味があると感じています。
- 「今日も一日よく頑張ったね」と、親子で同じ時間を共有できる
- 息子だけが特別扱いされるのではなく、「みんなでやる習慣」になっている
- 体をゆっくり動かすことで、寝る前の緊張が少しほぐれる
ストレッチが終わると、息子はお気に入りの猫のクッションを抱えて布団に入ります。
その姿を見ると、「今日もしんどい時間はあったけど、最後は少し笑顔で終われたかな」と思えます。
途中でやめたくなる日もありましたが、「無理のない範囲で続ける」という形で今も続けている習慣です。
仕事を休んででも、子どものそばにいると決めたときの気持ち
わが家の場合、私は仕事を長期で休む決断をしました。
もちろん、これはどの家庭でもできる選択ではありませんし、正解でも不正解でもありません。
あくまで「うちの場合はこうだった」という一例です。
毎日のように息子がお腹を押さえて苦しそうにしている姿を見ているうちに、
- 「今、この子のそばにいる時間を一番優先したい」
- 「勉強よりも、まずは“安心できる土台”を一緒に作りたい」
と強く感じるようになりました。
仕事を休むことには、不安もたくさんありました。
収入のこと、キャリアのこと、家族の生活のこと…。
それでも、あのタイミングでそばにいる選択をしたこと自体は、今も後悔していません。
息子にとっても、
- お腹が痛いときに、すぐ近くに親がいる
- 病院に行くとき、一人で頑張らなくていい
という状況は、少し安心材料になっていたのではないかと思います。
繰り返しになりますが、「仕事を辞めたり休んだりすべき」という話ではありません。
それぞれの家庭や状況によって、できる選択は違うはずです。
ただ、親として
- 「今の優先順位は何か」
- 「この子にとって一番安心できる形は何か」
を考えて決めたことは、どんな選択であっても、きっと子どもには伝わっていくのではないかと感じています。
同じように過敏性腸症候群の小学生と向き合う親御さんへ
まずは「うちだけじゃないんだ」と思ってほしい
子どもが毎朝「お腹が痛い」と言って学校に行けない。
検査をしても「異常なし」と言われる。
親としては、心配と不安と戸惑いでいっぱいになると思います。
私もまったく同じでした。
- 本当に病気なのか
- 行きたくないだけなのか
- このまま学校を休ませていていいのか
頭の中で何度も同じことをぐるぐる考えました。
でも、IBSと診断されてから分かったのは、
「同じように悩んでいる親子がたくさんいる」ということです。
このページにたどり着いたということは、あなたもすでに「何とかしたい」「少しでも情報がほしい」と動き始めているはずです。
それだけでも、十分すぎるほど子ども想いの親だと私は思います。
病名が分かるまで、あきらめずに相談してほしい
わが家の場合、診断がつくまでに半年以上の時間がかかりました。
いくつもの病院に行き、検査もたくさんしました。
その過程は、親にとっても子どもにとっても決して楽なものではありません。
それでも、最終的に大学病院で
「これは小児の過敏性腸症候群(IBS)です」
と言われたとき、
- 命に関わるような大きな病気ではなさそうだという安心
- これからどう付き合っていけばいいのかを一緒に考えてくれる専門医の存在
この2つのおかげで、ようやく少し肩の力を抜くことができました。
「別の病院で聞いてみる」「専門医を紹介してもらう」
こうした一歩は、とてもエネルギーがいります。
でも、もし今の説明にどうしても納得がいかないときは、セカンドオピニオンも選択肢のひとつとして、心のどこかに置いておいてもいいかもしれません。
親が不安で当たり前。でも、子どもはもっと不安
IBSの本や記事を読んでいると、「親の不安は子どもに伝わりやすい」とよく書いてあります。
では、「不安をなくさなきゃ」と頑張るべきかというと、私はそうは思いません。
病名が分からない時期に不安になるのは、ごく自然なことです。
むしろ大事なのは、
- 親も不安だけれど、それ以上に子どもはもっと不安だろう
- だからこそ、正確な情報や体験談を知って、少しでも落ち着いて話を聞けるようにする
この視点を、一緒に持ってあげることだと感じています。
私自身、
- IBSについて情報を集めたこと
- 他の家庭の体験談を読んだこと
で、自分の不安が少しずつ和らいでいきました。
親が落ち着いて話を聞けるようになると、子どもも少しずつ、自分の不安やしんどさを言葉にしやすくなっていくように思います。
完璧な対応はできなくていい。「一緒に悩む親」で十分
IBSの子を持つ親として、「あのときの声かけは良くなかったな」と後悔することは、私にもたくさんあります。
- 「学校がイヤなんでしょ?」と決めつけて聞いてしまったこと
- 勉強の遅れが不安で、焦った気持ちのまま言葉をぶつけてしまったこと
それでも今思うのは、
完璧な親でなくてもいい。
子どもと一緒に悩みながら、少しずつ歩き方を探していければそれでいい。
ということです。
IBSは「すぐに治す」というより、波と付き合いながら、その子なりのペースで生活を整えていく病気だと感じています。
この体験談が、同じように「過敏性腸症候群の小学生」と向き合っているあなたの心のどこかに、少しでも「安心」を足せていたら嬉しいです。
なお、ここで書いた内容は、あくまで一家庭の体験談です。
薬や治療法を勧めるものではありません。
お子さんの症状や治療については、必ずかかりつけの先生と相談しながら進めてください。

